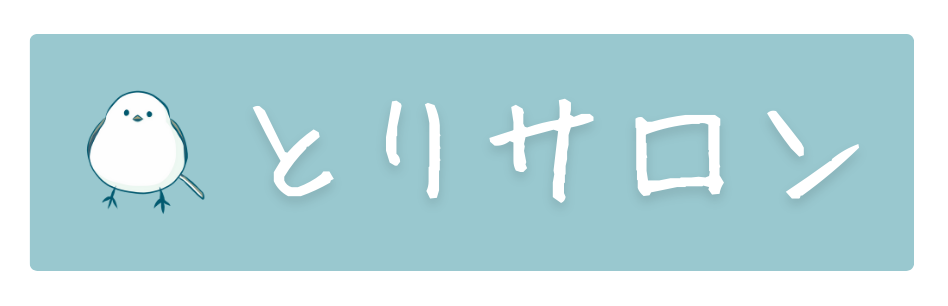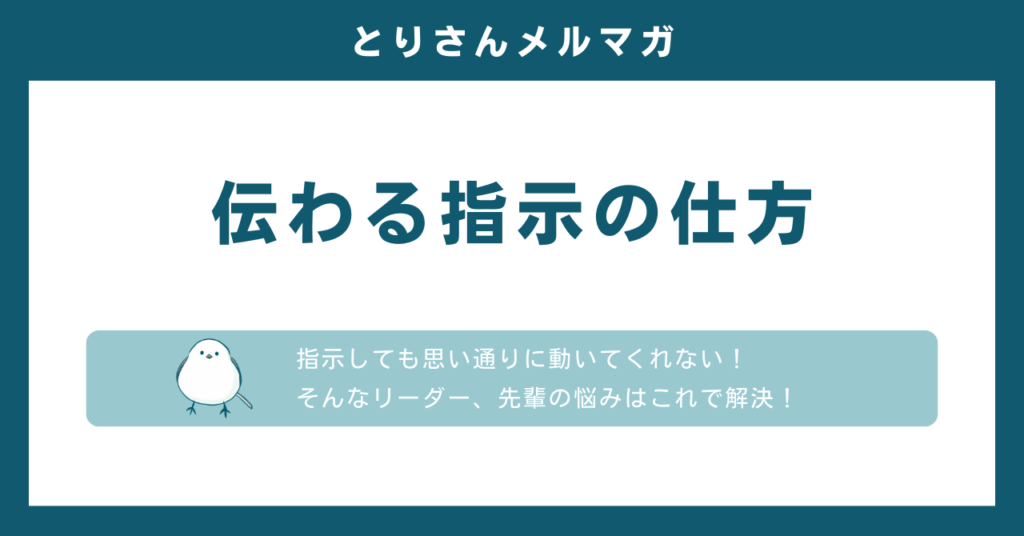
部下やチームメンバーに指示をした経験はありますか?
指示というと偉そうなニュアンスに聞こえるかもしれませんが、依頼やお願いという風に言い換えても良いと思います。
- 「やれって言われたことしかしない」
- 「(ミスに対して)言わなくてもわかるでしょ」
- 「普通は期限の数日前に一旦提出するでしょ」
誰かに指示したとき、一度は経験したことがあるんじゃないかな?という内容だと思います。
さて、これは指示した相手の理解力や器用さ、気がきくかどうかが問題なのでしょうか?
と聞かれると、答えは「NO」ですよね!
要するに、適切な指示をすることで、部下に期待通りの動きをしてもらいやすくなるということです。
もちろん部下の能力に依存する要素もありますが、それは指示側がコントロールできない要因です。
自分の指示は適切だったのか?を考えることが部下と自分自身の成長につながります。
指示する際に伝えるべき3つのポイントがあります!
- 目的
- 進め方
- 期限
この3つのポイントを理解していきましょう!
○業務の目的
業務には必ず目的があります。
具体的な業務内容と合わせて、目的も一緒に伝えるようにしましょう。
例えば、施設で入居者に薬を飲ませる際、2名でクロスチェックをしてから内服させるという業務があります。
指導者が内服させる際、部下に「これを一緒にチェックしてくれる?」とだけ指示するとします。
すると部下はひとまず「はい」と返事をしますが、それを行う目的については理解できていません。
忙しい中聞き返すこともできず、「言われたことだけやればいいか…」と業務を作業として行いました。
その業務の目的がわかっていないので、チェックするポイントや基準も曖昧になります。
その場は何も起こらなくても、重要性を理解していないまま作業として行うと、いずれミスや事故につながる可能性が高くなりますよね。
では業務の目的をしっかり伝えた場合はどうでしょう。
「万が一間違えて内服させてしまってはいけないので、服薬前のダブルチェックをお願いしても良い?」と部下に伝えたとします。
こう伝えることで、「他の入居者のお薬を間違えて飲ませてしまったら大変ですもんね!」という理解が働き、重要性が理解できます。
重要性が理解できると、その業務に対しての姿勢や緊張感が変わります。
さらに、間違いを減らすために別の良い方法を考えたりしてくれることもあるでしょう。
このように目的を明確に伝えることは、適切な指示をする上で重要なポイントの1つです。
○業務の進め方
伝えるべきポイントがあります。
- どのような手順で進めるか
- 手順の具体的な内容
- 手順でのポイント
の3つのポイントです。
例えばおむつ交換業務の場合…
- 準備
- 居室訪問
- おむつ交換
- 陰部洗浄
- 清拭
- 記録
というおおまかな業務の手順を示します。
次に、手順の具体的な内容を伝えます。
- おむつ交換を例に取ると…
- 声掛けを行う。
- 布団を畳む。
- ズボンを下げる。
- オムツを外す。
という具体的な内容を伝えます。
最後にポイントを伝えます。
- 排泄物に異常がないか?
- 皮膚に異常はないか?
- 不衛生なので外したおむつやパッとは床に置かない
などです。
このように予め大まかな手順と具体的な内容、ポイントを伝えておくと、理解がしやすいです。
業務の進め方を伝えるとき、やってしまいがちな良くない例があります。
それは、マニュアルにない経験則に基づいた対応を伝えることです。
おむつ交換を例に取ると、「エプロンや手袋は利用者さん毎に変えるのだけど、どうしても時間がないときは手袋だけ交換すれば大丈夫だから!」みたいなことです。
他にも、緊急時などのケースバイケースの対応を伝えるのもそうです。
気持ちは分かるのですが、経験が少ないスタッフにこのような伝え方をすると、「マニュアルと違うけど…」と違和感や混乱を招いたり、忙しいときはマニュアルは守らなくて良いんだ!という間違った認識を持たせてしまうこととなります。
上記のようなことを伝える場合、なぜ手袋の交換だけで良いのか根拠を伝えた上で、周囲のスタッフと相談して対応していくように伝えましょう。
そうすることで、基本はすべて交換することがルールであること。その対応が取れない場合は仲間や上司に相談すれば良いと理解してもらえます。
業務の進め方を伝える場合、マニュアルと経験上で得た知識は区別をして伝えなくてはいけないということです。
マニュアルは安全のための厳守すべきルールです。
一方、経験上の得た知識は応用です。どの場面でも正しいというわけではないので、経験が少ない職員が判断の材料とするには非常に危険です。
得てきた経験をもとに伝えるのは、指導側としては気持ちの良いものですが、指導という役割を理解して基本的な業務を伝える責任のほうがずっと重要です。
○業務の期限
どんな仕事にも期限がつきものです。
なぜかと言うと、どんな仕事も「その仕事の完了を待っている人がいる」からです。
指導者はそのことを伝え、期限から逆算して計画的に着手するよう促す必要があります。
例えば、7日後までに研修資料を作成する依頼をするとします。
一度上司に確認して、資料を修正して本提出をするとなると、一体いつから着手しはじめれば良いのか?ということを合わせて指示する必要があります。
これを「7日後」という指示だけにしてしまうと、7日後に出来上がっていれば良いのか…という認識になってしまいます。
一般的に研修資料となると、一度上司や先輩にチェックをしてもらうことが多いです。
業務に不慣れな場合は業務の逆算がうまくできないので、期日を伝えるだけでは難しいですね。
伝えるときは「7日後までに資料を作ってください。事前に一度チェックしたいので、4日後までに一度私に見せてくださいね」などと伝えましょう。
このような経験から、いずれ指示がなくても自分で逆算して業務を組み立てられるようになります。
○指示とは?
指示とは、「命令」ではなく「依頼」や「お願い」と考えたほうが良いかなと思います。
先輩の指示は絶対!というような一方通行なものではなく、後輩も疑問に思ったことがあれば意見できなければいけません。
疑問については一緒に考え、解決していくことで互いの成長に繋げていけます。
言い換えれば指示とは権限です。権限には責任が伴います。
指示の結果が悪かったとしたら、それは指示する側に問題があるということ。
指示する側が勘違いしないことも重要な要素になりますので、指導の際は注意しましょう!